アントン・チェーホフ
この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2010年12月) |
| アントン・チェーホフ | |
|---|---|
 | |
| 誕生 | 1860年1月29日 |
| 死没 | (1904-07-15) 1904年7月15日(44歳没) |
| 職業 | 作家、劇作家 |
| 国籍 | ロシア |
| 配偶者 | オリガ・クニッペル(1901年 - 1904年) |
| サイン | 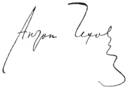 |
アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフ(ロシア語Антон Павлович Чехов:アントーン・パーヴラヴィチ・チェーハフ/ラテン文字(英文表記)Anton Pavlovich Chekhov、1860年1月29日・タガンログ - 1904年7月15日・バーデンワイラー)は、ロシアを代表する劇作家であり、多くの優れた短編を遺した小説家。
目次
1 生涯
2 評価
3 人物像の変遷
4 没後の影響
5 作品
5.1 戯曲
5.2 推理小説など
5.3 ノンフィクション
5.4 主な短編小説
6 日本語文献
6.1 主な作品集
6.2 文庫訳書(近年刊)
6.3 回想ほか
6.4 伝記研究
7 脚注
8 関連項目
9 関連人物
10 外部リンク
生涯

作家アントン・チェーホフ記念館(タガンローグ)。
アントン・チェーホフは、父パーヴェル・エゴーロヴィチ・チェーホフと、母エヴゲーニヤ・ヤーコヴレヴナ・チェーホワの3男として生まれた。兄にアレクサンドル、ニコライ、弟にイヴァン、ミハイル、妹にマリヤがいる。父方の祖父エゴールは農奴だったが、領主に身代金を支払って一家の自由を獲得した。父パーヴェルはタガンログで雑貨店を営んでいた。
1876年に一家は破産し、夜逃げしてモスクワに移住した。しかしアントンだけがタガンログに残ってタガンログ古典科中学(en)で勉学を続けた。この頃から詩や戯曲などを書いていたといわれていて、作品名こそ伝えられてはいるが、作品そのものは現存していない。
1879年に中学を卒業してモスクワに移り、モスクワ大学医学部に入学した。アントーシャ・チェホンテーなど複数のペンネームを用いて雑誌にユーモア短編を寄稿するようになった。学業と作家活動を兼ねる多忙な日々を送り、アントンの友人が家を訪れると、父であるパーヴェルが「いまアントンは忙しいから」と来訪を断ることも多々あったという。1884年には医学部を卒業し、医師としての資格を得、また実際に医師として診察などを行うようになった。こういったエピソードが伝えるとおり早熟な男子であり、母エヴゲーニヤや妹マリヤは「アントンが泣いたことは見たことが無い」と回想している。
作家として駆け出しの頃のチェーホフがユーモア短編を主に書いていたことはよく知られているが、それは生活費を得るためという現実的な要請によるものだった。いわゆる「本格的な」作家への転機となったのは1886年に老作家、ドミートリイ・グリゴローヴィチから激励と忠告を受けたことだったといわれている。グリゴローヴィチはチェーホフの文筆家としての才能を称賛しつつ、ユーモア短編の量産はせっかくの才能を浪費するものだと警告したのだった。これを機にチェーホフは文学的な作品の創作に真摯に取り組むようになり、「幸福」、「芦笛」、「曠野」、「ともしび」などの優れた作品が生まれたとみることもできよう。
1887年に書かれた初の本格的な長編戯曲『イワーノフ』は翌1888年の初演の評判こそよくなかったものの、1889年にサンクトペテルブルクのアレクサンドリンスキイ劇場での再演[1]は好評を博した。チェーホフは文壇の寵児となり、おどけて自らを「文壇のポチョムキン」と呼びさえした。当時の書簡には、ペテルブルクの道を歩くだけで花束を投げ込まれ、女性たちに囲まれたことが記されている。この頃に書かれた「退屈な話」(1889年)は、人生の意味を見失った老教授の不安と懐疑に苛まれたわびしい心情を描いた作品であるが、レフ・トルストイの短編『イワン・イリイチの死』を下敷きにしたことをたびたび指摘されるように、当時のチェーホフがレフ・トルストイの思想に傾倒していたことが知られている。
1890年の4月から12月にかけて、チェーホフは当時流刑地として使用されていたサハリン島へ「突然」でかけ、過酷な囚人たちの生活や環境をつぶさに観察し記録を残した[2][3]。この時の見聞は旅行記『サハリン島』(露: Остров Сахалин)としてまとめられて出版されており、サハリン旅行を作家チェーホフの転機とみなす指摘は少なくない。翌1891年には新聞社を経営していたアレクセイ・スヴォーリンとともに西ヨーロッパを訪れた[4]。スヴォーリンはチェーホフの作品をいくつも出版していた人物であり、2人は長く親密な友人関係を築いていた。しかしドレフュス事件を受けてアルフレド・ドレフュスを擁護したチェーホフはスヴォーリンと対立し、両者の関係は決裂するに至る。

チェーホフとオリガ・クニッペル
1892年にメリホヴォに移り住み、ここで1895年の秋に長編戯曲『かもめ』を執筆した。この作品は翌1896年秋にサンクトペテルブルクのアレクサンドリンスキイ劇場で初演されたが、これはロシア演劇史上類例がないといわれるほどの失敗に終わった、と長年いわれてきたが、最近の研究では、むしろ成功をおさめた部類なのではないかともいわれている。2年後の1898年にはモスクワ芸術座によって再演されて大きな成功を収め、チェーホフの劇作家としての名声は揺るぎないものとなった。モスクワ芸術座はこの成功を記念して飛翔するかもめの姿をデザインした意匠をシンボル・マークに採用した。
この1898年にチェーホフはヤルタに家を建て、翌1899年に同地に移り住んだ。ここで短編小説「犬を連れた奥さん」などを執筆した。またこの1899年にはモスクワ芸術座で『ワーニャ伯父さん』が初演され、1901年には同じくモスクワ芸術座で『三人姉妹』が初演された。この時マーシャ役を演じた女優、オリガ・クニッペルと同年5月に結婚した。
1904年には最後の作品『桜の園』がやはりモスクワ芸術座によって初演された。『桜の園』が初演された1月17日はチェーフの44歳の誕生日であり、チェーホフ筆歴25年の祝賀が兼ねられていた。だがチェーホフはすでに病み衰えており、舞台に立ち続けることはできなかった。同年6月に結核の治療のためドイツのバーデンワイラーに転地療養したが、7月15日に同地で亡くなった。最後の言葉はドイツ語で「私は死ぬ」であったと伝えられる。現在はノヴォデヴィチ墓地に葬られている。
評価
アントン・チェーホフはロシア文学の中で、あるいは世界文学史でも有数の巧みな小説作家である。
チェーホフは短編小説により、19世紀末にロシア文学史の流れに革命を起こしたといえる。当時ロシアの文壇では長編こそが小説であるという風潮が強く、チェーホフのように第一線で短編小説を絶えず発表した書き手はいなかった。しばしばフランスのギ・ド・モーパッサンとも比較されるが、伏線を計算して配置するプロットに技巧を凝らした小説にはあまり関心をもたなかったとされる。モーパッサンが出来事に焦点を当てたのに対し、チェーホフは人物に目を注いだといえるかもしれない。典型的なチェーホフの物語は外的な筋をほとんど持たない。その中心は登場人物たちの内面にあり、会話の端や細かな言葉、ト書きに注目するほかない。しばしば語られることではあるが、チェーホフの小説や劇においては何も起こらない。あるいはロシア人研究者チュダコーフが指摘するように、「何かが起こっても、何も起こらない」。チェーホフが内面のドラマを展開させる独自の手法をもっていたことは疑いようもないだろう。
小説だけでなく、チェーホフは最晩年の作品である戯曲『かもめ』、『三人姉妹』、『ワーニャ伯父さん』、『桜の園』の作者として、伝統的な戯曲と対極を成す新たな領域を切り開いた劇作家でもある。これらの作品の与えたインパクトの多くは、例えば『かもめ』の終幕に代表される巧みなアンチクライマックス(遁辞法)による。
演劇革命を起した。一に、主人公という考え方を舞台から追放した。二に主題という偉そうなものと絶縁した。三に筋立ての作り方を変えた[5]。
人物像の変遷
ソ連時代には「文豪チェーホフ」というイメージに適う「紳士チェーホフ」という人物像が政治的にあてはめられていた。当時出版されたチェーホフ全集などで、家族がそれにあてはまらない箇所を削除したことがわかっている。日本でも、チェーホフ作品の翻訳者として知られた神西清による「チェーホフは酒を絶っていた」などの言葉で知られているように「紳士チェーホフ」像は一人歩きをしていたといえる。しかし、チェーホフはむしろ酒豪の部類に入る人間であったし、書簡などを読めばいわゆる「下ネタ」を嫌っていたわけでもなく、オリガとの交際中も複数の女性と関係を持っていたことは伝記的な事実である。彼が「文豪」であったことは間違いないが、こういった紳士的でない「人間臭い」側面もまたチェーホフの魅力であることはいうまでも無いだろう。
チェーホフ自身は、象徴主義的な方法による演劇を嫌っており、『かもめ』の中でコスチャの劇中劇としてパロディー化したが、同時に象徴派の詩人モーリス・メーテルリンクから、大きな影響を受けたとも告白している。他に影響を受けた劇作家に、イプセンがいる。『かもめ』は、イプセンの『野鴨』(チェーホフが、気に入っていた作品のひとつ)抜きに、今日演じられるものには成らず、全く書かれなかった可能性もあった。
没後の影響
没後ロシア文学界ではチェーホフの評価は高かったものの、第一次世界大戦最中、コンスタンス・ガーネットによって作品が英訳された後も国際的な評価は低かった。
しかしチェーホフの評論家の鋭い分析に挑む挑戦的な文学スタイルで、1920年代からイギリスではチェーホフの戯曲が人気を博し、今日ではイギリス演劇の代表的なものとなっている。またアメリカ演劇界は写実的な演劇を上演するスタニスラフスキーの演出技巧の影響を経た後、それに遅れるような形でチェーホフの影響が次第に強くなってくる。テネシー・ウィリアムズやアーサー・ミラー、クリフォード・オデッツなども好んでチェーホフの技法を用いている。
イギリスの演劇作家であるマイケル・フレインは、チェーホフのおどけた家族が見る社会に焦点を置いて描く作風に影響を受けた作家としてよく挙げられる。短編作家の多くも同じように少なからず、チェーホフの影響は受けている。その代表格としてキャサリン・マンスフィールドやジョン・チーヴァーがいる。またアメリカの作家のレイモンド・カーヴァーもチェーホフのミニマリズム的な散文に影響を受けているし[6]、イギリスの短編作家のV・S・プリチェットもチェーホフの作品から影響を受けている。以上のことを見ても、チェーホフは様々な作家に多大な影響を与えていることが分かる。
またチェーホフの作品を元に制作された映画では、エミーリ・ロチャヌーの『My Tender and Affectionate Beast』(1978年)や、ニキータ・ミハルコフとマルチェロ・マストロヤンニの合作の『Dark Eyes』(1987年)、ルイ・マルの『Vanya on 42nd Street』(1994年)、アンソニー・ホプキンスの『August』などがあり数え上げればきりがない。
作品
戯曲
- プラトーノフ(1881年) - 一幕
- タバコの害について(1886年、1902年)
- イワーノフ(1887年) - 四幕
- 熊 (1888年) - 一幕
- 結婚申し込み(1888年 -1889年) - 一幕
- 森の精(1889年) - 四幕
かもめ(1896年)
ワーニャ伯父さん(1899年-1900年) - 『森の精』の改作
三人姉妹(1901年)
桜の園(1904年)
推理小説など
狩場の悲劇(ロシア語Драма На Охоте)The Hunting Ground Tragedy (1884年) - 異色の長篇推理小説- 安全マッチ(безопасная спичка)Safety matches (1884年)
- 長靴(резиновые сапоги)The Wellington Boots (1885年)
ノンフィクション
- サハリン島(1895年)
- 原卓也訳 「サハリン島」 中央公論新社(新書判)、2009年
- 松下裕訳 「チェーホフ全集 12 シベリアの旅・サハリン島」 ちくま文庫、1994年、復刊2009年
主な短編小説
- かき(1884年)
- カメレオン(1884年)
- 曠野(1888年)
- ともしび(1888年)
- ねむい(1888年)
- 退屈な話(1889年)
- グーセフ(1890年)
決闘[7](1891年)- 妻(1892年)- この作品にヒントを得て制作されたトルコ映画『雪の轍』
- 六号室(1892年)
- 恐怖(1892年)
- 黒衣の僧(1894年)
- ロスチャイルドのヴァイオリン(1894年)
- 学生(1894年)
- 文学教師(1894年)
- 三年(1895年)
- アリアドナ(1895年)
- 殺人(1895年)
- 中二階のある家(1896年)
- わが生活(1896年)
- 百姓ども(1897年)
- 荷馬車で(1897年)
- 箱にはいった男、すぐり、恋について(1898年) - 三部作
- イオーヌィチ(1898年)
- 往診中の出来事(1898年)
- 新しい別荘(1898年)
- 役目がら(1898年)
- かわいい女(1899年)
犬を連れた奥さん(1899年)- クリスマス週間に(1899年)
- 谷間(1899年)
- 僧正(1902年)
- いいなずけ(1903年)
日本語文献
主な作品集
- 『チェーホフ全集』 神西・原・池田編(全16巻、中央公論社)-最終2巻は書簡集、新版は数度刊行
- 『チェーホフ全集』 松下裕訳(全12巻、筑摩書房)-ちくま文庫で新版刊行
- 『チェーホフ・ユモレスカ』 松下裕訳(全3巻、新潮社)
- 『チェーホフ小説選』、『チェーホフ戯曲選』 松下裕訳(水声社)
- 『チェーホフ・コレクション』 工藤正廣・児島宏子・中村喜和訳(全23巻、未知谷)
文庫訳書(近年刊)
- 『かもめ・ワーニャ伯父さん』 神西清訳(新潮文庫 改版2001年)
- 『かわいい女・犬を連れた奥さん』 小笠原豊樹訳(新潮文庫 改版2005年)
- 『桜の園・三人姉妹』 神西清訳(新潮文庫 改版2011年)
- 『カシタンカ・ねむい 他七篇』 神西清訳(岩波文庫 2008年)
- 『チェーホフ・ユモレスカ 傑作短編集 Ⅰ』 松下裕訳(新潮文庫 2008年)
- 『チェーホフ・ユモレスカ 傑作短編集 Ⅱ』 松下裕訳(新潮文庫 2009年)
- 『郊外の一日 新チェーホフ・ユモレスカ(1)』 松下裕訳(中公文庫 2015年)
- 『結婚披露宴 新チェーホフ・ユモレスカ(2)』 松下裕訳(中公文庫 2015年)
- 『子どもたち・曠野 他十篇』 松下裕訳(岩波文庫 2009年)
- 『ともしび・谷間 他七篇』 松下裕訳(岩波文庫 2009年)
- 『六号病棟・退屈な話 他五篇』 松下裕訳(岩波文庫 2009年)
- 『かもめ』 浦雅春訳(岩波文庫 2012年)
- 『かもめ』 沼野充義訳(集英社文庫 2012年)
- 『チェーホフ短篇集』 松下裕編訳(ちくま文庫 2009年)、代表作全12篇
- 『チェーホフ集 結末のない話』 松下裕編訳(ちくま文庫 2010年)、全51篇の超短編
- 『ワーニャ伯父さん・三人姉妹』 浦雅春訳(光文社古典新訳文庫 2009年)
- 『桜の園・プロポーズ・熊』 浦雅春訳(光文社古典新訳文庫 2012年)
- 『馬のような名字 チェーホフ傑作選』 浦雅春編訳(河出文庫 2010年)
回想ほか
オリガ・クニッペル 『夫チェーホフ』 池田健太郎編訳(麦秋社)- 『チェーホフ=クニッペル往復書簡』 牧原純・中本信幸編訳(全3巻、麦秋社)
- マリヤ・チェーホフ 『兄チェーホフ 遠い過去から』 牧原純訳(筑摩書房〈筑摩叢書〉、1992年)、旧版は未來社
- ミハイル・チェーホフ 『わが兄チェーホフ』 宮島綾子訳(東洋書店新社、2018年)
- 『チェーホフの思い出』 池田健太郎編訳(中央公論社)- 友人・近親者たちの回想、初版は「全集」別巻
- リディア・アヴィーロワ『チェーホフとの恋』 小野俊一訳(未知谷、2005年)
- リジヤ・アヴィーロワ『私のなかのチェーホフ』 尾家順子訳(群像社ライブラリー、2005年)- 同著の別訳
- ボリース・ザイツェフ『チェーホフのこと』 近藤昌夫訳(未知谷、2014年)
イワン・ブーニン『ブーニン作品集5 呪われた日々 チェーホフのこと』 佐藤祥子・尾家順子・利府佳名子訳(群像社、2003年)- 『チェーホフの風景』 ペーター・ウルバン編、谷川道子訳(文藝春秋、1995年) - 写真多数の文学アルバム
ウラジーミル・ギリャロフスキー『帝政末期のロシア人』[8]村手義治訳(中央公論社、のち中公文庫)
伝記研究
アンリ・トロワイヤ 『チェーホフ伝』 村上香住子訳(中央公論社、のち中公文庫)
原卓也編 『チェーホフ研究』(中央公論社) - 初版は「全集」別巻- ソフィ・ラフィット解説『チェーホフ自身によるチェーホフ』 吉岡正敞訳(未知谷)
- 松下裕 『チェーホフの光と影』(筑摩書房)
- 沼野充義 『チェーホフ 七分の絶望と三分の希望』(講談社)
浦雅春 『チェーホフ』(岩波新書)
牧原純 『北ホテル48号室 チェーホフと女性たち』(未知谷)- 牧原純 『二人のオリガ・クニッペル チェーホフと「嵐」の時代』(未知谷)
池田健太郎 『チェーホフの生活』(中央公論社)
- 他に 『「かもめ」評釈』(中央公論社)、遺作『チェーホフの仕事部屋』(新潮選書)がある。
佐藤清郎 『チェーホフへの旅』 (筑摩書房)※同書房で以下3冊を順に刊行。
- 『チェーホフの生涯』、『チェーホフ芸術の世界』、『チェーホフ劇の世界』
- 佐藤清郎『わが心のチェーホフ』(以文社)
- 『チェーホフの短篇小説はいかに読まれてきたか』 井桁貞義・井上健編(世界思想社)
- セルゲイ・ザルイギン 『わがチェーホフ』 岩田貴訳(群像社)
ロジェ・グルニエ『チェーホフの感じ』 山田稔訳(みすず書房)- ヴィリジル・タナズ 『チェーホフ ガリマール新評伝シリーズ世界の傑物』 谷口きみ子・清水珠代訳(祥伝社)
- 『文芸読本 チェーホフ』(河出書房新社) - 作家論集と短編・戯曲数編。
- エヴゲーニイ・バラバノーヴィチ『チェーホフとチャイコフスキー』中本信幸訳(新読書社)
脚注
^ この際劇場からの要求で戯曲の改訂が行われた。
^ この時チェーホフは現地の日本の外交官とも交流し、さらに日本へ渡航することも計画したが、これはコレラの流行のために断念せざるを得なかった。
^ 当時サハリン島は「囚人島」と呼ばれていた。
^ チェーホフが切手蒐集家であったという事実はよく知られているが、この旅行の際に彼はかつて手紙を送った親戚や友人の家を回って、その手紙から切手を剥がしてコレクションに加えていたというエピソードは興味深い。
^ 井上ひさし『この人から受け継ぐもの』(岩波書店 2014年)p.108. ただし、「三番目については多少の異論がある」としている。
^ レイモンド・カーヴァーはチェーホフの臨終の場面に焦点を当てた小説『使い走り』を書いている。なお同作品はカーヴァーが最後に書いた小説となった。
^ Dover Kosashvili監督により映画化された("Anton Chekhov's The Duel"、2010年)。
^ 「チェホンテ」のペンネーム時代から晩年までの交流の回想がある。
関連項目
チェーホフの銃 - チェーホフの言葉に由来するとされる、作劇上の定形的ルール。
関連人物
マクシム・ゴーリキー - チェーホフを師として慕ったロシアの作家、劇作家。
ピョートル・チャイコフスキー - 親交のあったロシアの作曲家。実現に至らなかったが共同でオペラを制作する計画があった。
セルゲイ・ラフマニノフ - 同じく親交のあったロシアの作曲家。『ワーニャ伯父さん』のセリフを元に歌曲(作品26の3)を作曲した。
マイケル・チェーホフ - 甥で俳優、演出家、モスクワ芸術座を主に俳優の育成にもあたった。
神西清 - 訳者、『ワーニャ伯父さん』の翻訳で文部大臣賞を受賞。
小野理子 - 訳者、岩波文庫 『桜の園』、『ワーニャおじさん』の訳者
木村彰一 - 訳者、講談社ほか。
中村喜和 - 訳者、「チェーホフ・コレクション」の訳者の一人。
渡辺守章 - フランス文学者、『かもめ』をフランス語訳を元に演出。
小田島雄志 - 戯曲を翻訳(白水社)。英語訳からの日本語訳という手法が翻訳のあり方をめぐる議論を喚起した。
沼野充義 - 訳者、『かもめ』や『かわいい女』(「かわいい」)ほか
宇野重吉 - 名優で演出家でも著名。
湯浅芳子 - 戦前からの訳者。
蜷川幸雄 - 多作品を演出。
千田是也 - 俳優座主宰、多作品を演出。
中村草田男‐俳人、7月15日の忌日を「チェーホフ忌」として俳句に使用し季語にした。
外部リンク
- 日本語
- アントン・チェーホフ:作家別作品リスト - 青空文庫
- アントン・チェーホフ 作品訳本リスト
- チェーホフの短編小説「たわむれ」を読む
チェーホフ名言集 (世界傑作格言集)
チェーホフ試論 神西清、『文芸』、1954年
- 外国語
- チェーホフの主要著作(ロシア語)
eTexts of Chekhov's works, at Project Gutenberg
- Official Web Site of the City of Taganrog, "Birthplace of Anton Chekhov"